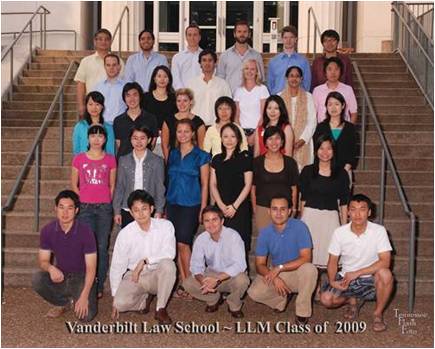J.D.攻略法その7 1年目の夏休み-安堵の章 [J.D.攻略法]
(1) Journal Competition(ジャーナル編集委員選考試験)
ジャーナルとは、課外活動の一つとして、2Lと3Lの学生が編集する法律論文集のことです。論文を投稿するのは主に学者・実務家で、編集委員である学生が、全ての選考および内容のチェックを行うところに特徴があります。特に学者にとって、論文を発表することは必須の目標・大きな実績であるため、学生が教授昇進のカギを握ることもあるのです。どのロースクールにも複数のジャーナルがあることが通常で、当校には、法律全般をカバーするLaw Review、国際法を扱うJournal of Transnational Law、音楽・映画・スポーツなどのエンターテイメント法や知的財産を扱う Journal of Entertainment and Technology Lawの3誌があります。
ジャーナルの編集委員になることは、ほぼすべての学生の目標です。編集の過程でリサーチ・ライティングといった必須の技術が身につきますし、最新のトピックや議論に触れ、一流の学者や実務家との関係も出来ます。その一方で、採用した論文について、本文および引用を細かくチェックするといった地道な作業もあり、土日もつぶれてしまうほど負担は重くなります。それでも人気があるのは、ひとえに就職活動や将来の弁護士人生において大きなアピールになるからです。一般に、ジャーナルのメンバーシップは、成績優秀で高いスキルがあることの証明と考えられています。教授や裁判官を目指すには必須ですし、大手の弁護士事務所に就職する学生のほとんどがジャーナルのメンバーです。
当校では、3つのジャーナルの2Lメンバーが約30名ずつ、つまり、1Lの227名から90名(約40%)のみがメンバーになることが出来ます。選考試験は各ジャーナル共通形式で行われ、基準は各ジャーナルによって多少異なりますが、1Lの学業成績と選考試験の結果が総合されます。総合成績の上位者から希望のジャーナルに振り分けられていくのですが、ほとんどの学生はジャーナルの「格」を重視し、Law Review、Journal of Transnational Law、Journal of Entertainment and Technology Lawの順で希望を出します。つまり、多少の例外もありますが、Law Reviewは学年の最優秀の30人、Journal of Transnational Lawはその次に優秀な30人が集まっていることになります。
春学期の中ごろに、選考試験の説明会が開かれ、ほぼ1Lの全員が出席し、教室は満杯になりました。とうていメンバーになれなさそうな学生もおり、私に対しても、なんだお前もか、というような態度を取る学生もいました。各ジャーナルの編集長がそれぞれスピーチを行ないましたが、みな堂々としており、さすがの貫禄でした。その後、教授による、「選考試験をいかに勝ち抜くか」についての講義までありました。「選考する側にとって最も重要なのは、いっしょに編集の仕事をするメンバーとしてふさわしいかどうか。だから、論文の内容そのものの良し悪しよりも、試験の形式を守り誤字脱字をなくすといった当たり前のことに気を配りなさい。また、添付されている参考資料は非常に難解であるから、それをいかに理解し、自分の分かりやすい言葉で説明できるかという能力も問われている」とのことでした。
ルールを守り細部に気を配るというのは、法律家として最も重要な資質の一つであり、ジャーナルのメンバーが就職で有利になることも頷けます。また、例年全体の8割程度が試験に申し込むものの、さらにその中ですべての試験を終えて提出するものは8割程度だそうです。つまり、単純計算で、227×0.8×0.8=145名が90の席を争うことになります。一見倍率は低いようですが、試験に申し込む学生はある程度自分に自信がある学生ですし、期末試験終了直後の夏休みにもかかわらず難しい課題を完成させて提出する生徒は相当にやる気がありますから、決して楽な競争ではありません。
春学期期末試験終了の3日後の月曜日、選考試験の課題配布が始まりました。自分で学校まで資料を取りに行き、2週間後の月曜日までに提出しなければなりません。試験の疲れも取りきれていませんでしたが、なんとか起きて9時半ごろに学校に行くと、既に30名程度が受け取りを完了していました。既に競争は始まっているのです。試験は無記名式で、添付の論文の文法・表現上の間違いや誤字脱字をチェックする「文法テスト」、引用例についてBluebookというルールブックのとおりに正しく訂正する「引用テスト」、および課題論文の三部構成でした
論文の課題は、ごく簡単に言うと「住民の海岸掃除活動は環境法に反するか否か」であり、問題の大まかな背景と、参考資料(法令、判例、論文など)が添付されています。添付資料以外の参照および他人との相談は厳禁されており、枚数も12枚に制限されています。そのため内容が似通うのは必至で、添付資料をいかに消化し、わかりやすく正確な論文を書くか、が勝負になってくるのです。添付以外の資料は使えませんから、「日本法ではこうなっている」などと言って独自性を出すことは出来ませんし、また、学校で日本法を知っているのは明らかに私だけなので、無記名試験という観点からも問題になるでしょう。
教授の指導どおり、まずチェックリストを作り、初日はコーヒー片手にリラックスして、ざっと資料を眺めて全体像をつかむにとどめました。その後2日間かけて「文法テスト」と「引用テスト」を一通り終了し、その後は添付資料の通読に取り掛かりました。1週間目に本文を書き始める予定でしたが、添付資料の大部分は相当に難解であり、また判例の数も多く、とても消化し切れませんでした。やっと本文を書き始められたのは2週間目の中ごろであり、最後の2日は徹夜して、締め切りまで4時間をきったところでやっと満足できるものが仕上がりました。ふらふらの体で提出に行き、家に帰ってからは、とりあえず成し遂げた満足感で死んだように眠りました。
その後1ヶ月は全く音沙汰が無く、やがて何度か「もうすぐ発表します」旨のメールが何度か届くようになりました。私も含め多くの学生はこの時期インターンをしていましたが、私達にとってはこの選考試験が夏の最大の関心事ですので、相当数の催促・問い合わせがあったようです。もしかしてもう合格者には直接お知らせが来ているのでは、などと半ばあきらめていた7月の終わりごろ、学校のホームページに合格者のリストが発表されたとのメールが届きました。怖くてとてもすぐに見ることが出来なかったので、とりあえずリストを印刷し、名前を紙で隠しながら一行ずつずらし、上から順番に合格者を見ていきました。私の名前は一向に見つからず、リストの最後にたどりつき、もうだめかと思った瞬間、Vanderbilt Journal of Transnational Lawの欄に自分の名前を見つけました。私の苗字はYで始まるため、アルファベット順のリストの最後のほうに来て当然なのですが、そんなことを考える余裕は無かったのです。
ジャーナルの表紙

あらためて選ばれたメンバーを見ると、Law Reviewには、いつもクラスの最後のほうで「まとめ」的発言をするJ君やS君をはじめとして、Vanderbilt Scholastic Excellence Award(成績最優秀賞)の常連が揃っています。私が所属することになるVanderbilt Journal of Transnational Lawも、普段から優秀さの目立つクラスメイトが数多く選ばれており、自分がこんなところにいてよいのだろうかと思いました。同じジャーナルに選ばれたセクションメイト達にメールを打ったところ、「頑張っていい雑誌を作っていこう」「いいメンバーが選ばれているね」などの返事が次々と返ってきて、すでに良い意味での「仲間意識」が醸成されつつあるのを感ました。日本人LL.M.の友人からは、「日本の誇りだ」と、中国人LL.M.の友人からは、「アジアの誇りだ」と褒められました。
入学前のキャンパスビジットでお世話になった別のロースクールのある教授にもメールしたところ、「きみのジャーナルは国際法で最も定評のあるものの一つだ。実は、私も8月に論文を君のジャーナルに提出する予定なので、よろしく頼む」とのメッセージを頂きました。私は2Lのヒラ編集員で論文選定の権限は無く、もちろん教授もそれはご存知でお世辞を言ってくれているのですが、なんだか国際法学会の一旦を担うメンバーになれたような誇大妄想を抱くほどでした。ちなみに、専門家の編集するジャーナルを含めた全米の国際法ジャーナルランキングでは、わがジャーナルは第8位にランクされています。
一方で、何人かの「誰もが認める優等生」や「クラスでよく発言する熱心な生徒」が落選していました。ある優秀な学生が、試験問題は受け取りに行ったものの、サマーインターンとの両立が出来ず、結局棄権してしまったという話も聞きました。私以外の留学生では、カナダ人のK君、オーストラリア人のLさんは選ばれたものの、中国人のS君とR君、ナイジェリア人のO君は選ばれませんでした。今まで、Scholastic Excellence Awardを除いて、名前が公表されることはありませんでしたし、学生同士でも成績を話し合ったりはしませんから、だれが出来て誰がそうでないかは、本当のところは分かりませんでした。しかしこのジャーナルの選考で、明らかな「勝ち組」と「負け組」が分かれてしまったと言っても過言ではなく、あらためてロースクールでの競争の非情さを感じました。
(2)夏休みのインターンシップ
ロースクールの夏休みは、約3ヶ月間と、非常に長いものになっています。かつては、学期中にはできない旅行をするなど、まさに「休み」として過ごす生徒もいたようです。卒業後は、2L終了後の夏休みにインターンをした弁護士事務所に就職するパターンがほとんどですので、1L終了後のインターンは就職に直接の関係は無いと言われています。しかし、実務経験を得る貴重な機会ですし、レジュメにも書くことが出来ますので、現在では何らかの法律関連の仕事をするのが通例となっています。
最も人気の高いインターン先は法律事務所です。しかし、法律事務所側の事情として、1Lは技能に乏しくまた就職と直接は結びつかない(2年目のインターン先に取られてしまう可能性が強い)ため、よほど1L秋学期の成績が優秀か、何らかのコネがない限り、1Lを雇うことはありません。そこで、多くの学生は次善のインターン先として、裁判所・検察もしくはその他の政府機関などを選ぶことになります。
私の場合は、幸運にも会社時代の先輩の伝で、NYCにあるDという弁護士事務所で働けることになりました。DはNYCでトップ10に数えられる名門事務所であり、「もぐり」である私をのぞいて、インターンは全て2Lで、イェール・ハーバード・コロンビア・NYUといった超一流のロースクールの学生が8割方を占めます。
仕事では、入社数年目のアソシエイトの仕事を手伝って、簡単な契約書の作成や、日本法に関連するリサーチなどをさせてもらうことが出来ました。インターンといっても一日中働いている訳ではなく、毎日必ず何かしら、先輩弁護士が業務について説明するセミナーや、ライティング・ネゴーシエーションなどの実務訓練があります。アフター5は、大リーグ観戦、美術館や動物園を貸切ったパーティー、土日になるとカヌーツアーやカントリークラブでのイベントなど、盛り沢山の内容でした。こうしたイベントは、優秀な学生をひきつけるための手段として、多くの事務所で慣例となっているのです。
NYの巨大事務所というと、だれもが死ぬほど働いている、という姿を想像していました。しかし、実際の彼らは、個人主義を貫くアメリカ人らしく、家族や自分の時間を大切にしており、それらを犠牲にしてまで働くのは格好が悪いと思っているふしがあります。また弁護士は、たとえば「Xという顧客のYという契約書にZ分使った」というように、一つ一つの仕事を分単位で詳細に管理しており、それを元に顧客への請求をしています。顧客に請求できる仕事がなければオフィスに残っていても仕方がないため、つきあい残業などはありえません。もっとも顧客の要求があれば徹夜の連続も辞さず、とくに若いアソシエイトなど何日もオフィスに泊り込むこともあるようです。
さて、ジャーナルのメンバーに選ばれて有頂天の私でしたが、メンバーになるということはそれだけの義務が伴います。なぜ2Lが死ぬほどつらいといわれるのか、私も理解するときがまもなくやってくるのですが、それは次のお話で。。。