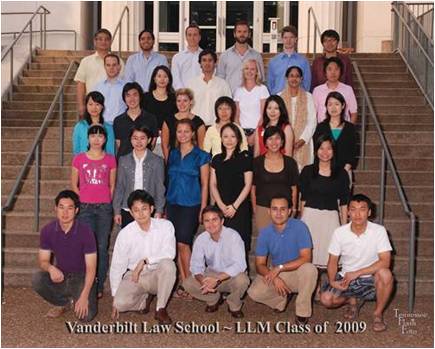J.D.攻略法その8 死ぬほどつらい2L-秋学期-混沌の章 [J.D.攻略法]
さて、死ぬほど怖い1Lを何とか生き残り、念願のジャーナルのメンバーになった私でしたが、その先には死ぬほどつらいといわれる2Lが待っていました。確かにロースクールにも慣れ、精神的には多少楽になったかもしれません。しかし、2Lでは通常の授業に加えて、ジャーナル活動、そして来夏のインターンシップを得るための就職活動が始まり、そのやりくりに自分を極限まで追い詰めることになるのです。
(1) オンキャンパスインタビュー(一次面接)
ロースクールの学生の就職活動は、2Lの秋学期に本格化します。名目上は2L終了時の夏休みのインターン先探しではありますが、インターン終了後には卒業後の就職のオファーももらえるのが通常であるため、実際は卒業後の就職先を探すのと同じことになります。例えば、NYの大規模事務所の場合、インターンに対する卒業後の就職のオファー率は95%以上といわれています。オファーをもらえない理由は仕事以外の問題が多いそうで、たとえば、「自分はインターンとして、毎日パーティー三昧のいかに楽しい生活を送っているか」という友達宛のメールを間違って所内全員に転送してしまった学生や、パートナーの奥さんとやんごとなき関係になってしまった学生などがいると聞きます。
就職活動は通常、オンキャンパスインタビュー(一次面接)およびコールバックインタビュー(二次面接)に分かれます。オンキャンパスインタビューとは、全国各地の事務所がロースクールのキャンパスを訪問して行う面接のことです。もちろん事務所のリソースも限られていますから、事務所の「格」とロースクールの「格」を勘案して、最大限良い学生をとれそうな学校を訪問するという駆け引きが行われます。ロースクールの就職課にとっても、いかに格の高い事務所をキャンパスに呼ぶかというのが腕の見せ所です。仮にオンキャンパスインタビューをしない事務所の面接を受けたければ、履歴書を直接送るしかありませんが、そのロースクールの学生には基本的に興味がないということですから、面接に呼ばれる可能性はほとんどありません。
バンダービルトは、ナッシュビルという南部の中核都市にあることから、東海岸や西海岸にある事務所の就職については地理的に不利になることは否めません。しかし、卒業生と学校の努力によって、当校を訪問する事務所は年々増えています。たとえば、私が2Lのときは、全体で200以上の事務所が当校を訪問し、特にそのうちVault社による全米弁護士事務所ランキング30位以内のうち20以上の事務所が含まれていました。同ランキングのトップ50の事務所における就職率というデータでは、バンダービルトは全米で第15位にランクされています。
2Lの人数は225人ですが、一つの事務所がオンキャンパスインタビューをする人数は10~20人といったところです。そのため、次のような入札方式が取られています。まず学生は、面接を希望する事務所を1番から最大40番まで順番を付けて提出します。面接希望者が面接枠より多い場合は、事務所側が30%、学校側が70%の選択権を持つことになっており、事務所側は学校の成績と履歴書で選び、学校側は単純にその事務所の希望順位が上の学生から選んでいきます。つまり、成績や経歴が素晴らしければ、希望の面接をほぼ100%受けることができます。一方で、成績や経歴がそれほどではなくても、希望順位が高ければ高いほど、そして事務所の人気が低ければ低いほど、面接を受けられる確率も高くなります。
全米弁護士事務所ランキング上位に入るような事務所は、「成績上位x%のみ」「成績3.xxx以上」「ジャーナルのメンバーであること」などと、面接を受けるための最低条件や望ましい条件を要求しています。また、学生側でも、自分の成績と経歴で受かりそうな事務所を選ぼうとします。そのため、事務所のランキングと人気度は必ずしも比例しません。一方で、あまり人気のない事務所では面接枠が埋まらないこともあり、その場合は当日の飛び込み面接も受け付けていたりします。
私の場合、200以上の弁護士事務所から、「東京に事務所がある」もしくは「国際展開している」という2点を基準に、面接を志望する事務所をリストアップしました。しかし問題は、この2点を満たす事務所のほとんどが大都市に拠点を置き、全米ランキングも高いいわゆる「格の高い」事務所であることです。特に9つの事務所では、私の1Lの成績では必要最低条件を満たさず、門前払いをくらってしまう状況でした。しかし、1Lを生き残ることで多少ずうずうしさを身につけたのか、もしくはもともとの性格からなのか、だめもとで、「自分は条件を満たさないが、国際的な法律業務の経験もあり必ずや役立つであろうから、面接を受けさせてほしい」というメールと履歴書を送ってみました。
すると驚くことに、2つの事務所からは「是非受けてください」との返信がすぐにありました。もう1つ別の事務所からは、「成績基準は絶対なので、残念です」との丁寧な返信がありました。残りの6事務所からは当然のごとく無視されましたが、本来無理なお願いをしているのはこちらですから、上々の結果でした。結局私は全部で30の事務所の面接を申し込み、その半分の15の事務所の面接を受けられることになりました。希望順位の低い事務所はほとんど抽選に外れてしまい、周囲に聞いても、10~20の面接を受ける学生がほとんどでした。
面接は全て平日の日中に組まれており、授業を抜け出して面接を受けることもしばしばでした。若い学生の中には、まだスーツを着慣れておらずスニーカーを合わせてしまうものもおり、かつての日本での就職活動を懐かしく思いました。また、この時期には既にジャーナルの仕事も始まっており、ジャーナル・授業・面接の困難な三立が要求されました。ジャーナルの仕事が徹夜になってしまい、一睡もせず面接を2つ連続で受けたこともありました。その面接は思いのほかスムーズに進んだように感じたのですが、それが自分の英語が上達したためなのか、単に頭が朦朧として現実を認識していなかったのかは定かではありません。
実際の面接は15分程度なので、「なぜこの事務所か」「なぜロースクールに来たか」「なぜこの都市か」といった基本的なことしか聞かれません。一般的に、二次のコールバックに呼ばれるのは10~20%で、事務所の側でも、成績と履歴書で面接前にほぼ当たりを付けているといわれています。面接官はほとんどがバンダービルトの出身で、しかもジャーナル経験者が多く、ジャーナルの話が弾むこともしばしばありました。一方で、NYとLA以外にある事務所では、なぜその都市かということがうまく説明できず、気まずい雰囲気になってしまうこともありました。
2番目に面接を受けたNYのある事務所からは、面接の翌日に一次通過のしらせが電話であり、数週間後に現地で二次面接を受けられることになりました。入学試験のときとは違って、幸先の良いスタートでした。一方で、面接でも面接官があきらかにやる気を見せていなかったいくつかの事務所からは、一週間ほどで「I regret . . . 」で始まる薄っぺらい例の不合格通知が届きはじめました。その他の事務所からは音沙汰が無く、就職課の「便りの無いのは良い知らせ(No news is good news)」という言葉を頼りに、吉報を待ち続けました。合格通知は通常電話で来るといわれているため、帰宅して電話に着信履歴があるたびに気分が高揚するものの、どきどきしながら留守録メッセージを聞いてみるとクレジットカードの勧誘、という落胆の日々が続きました。
(2) コールバックインタビュー
コールバックインタビューとは、オンキャンパスインタビューの合格者を、事務所の本拠まで招いて行う二次面接のことです。飛行機代、食事代、ホテル代など、すべて事務所持ちとなります。1L時の成績が良いと、面接を受けたほとんどの事務所からコールバックをもらうこともあります。同じジャーナルのメンバーで、3Lの時には編集長になることになるKさんなどは、1週間かけて全米各地の8事務所を訪問するそうで、こうなるとちょっとした大名旅行気分でしょう。
コールバックは半日掛けて行われ、パートナーおよびアソシエイトそれぞれ数人と個別に20~30分の面接をした後、ランチもしくはディナーに行くのが通例です。私の場合、パートナー2名、アソシエイト1名と面接後、別のアソシエイト2名とランチに行きました。パートナーの一人は、「私も忙しいんでどんどん行くよ」と、矢継ぎ早に質問を投げかけてきました。最後に何か質問はないかと聞かれたので、「新人アソシエイトに何を求めますか?」と聞いたところ、「完璧であること(perfection)」と、真顔で答えられました。
その後面接を受けた3人のアソシエイトは、年齢が近いこともあってか、「何でも聞いてくれ」というような気さくな雰囲気でした。私もなるべく多くの質問をして、少しでも興味があることをアピールしようと努めました。全部で約3時間程度のコールバックでしたが、終了後は疲労困憊で、もう二度と受けたくないというのが正直な感想でした。とにかく頭を休めたかったので、NYの紀伊国屋でマンガを買い込み、帰りの飛行機の中で読みふけりました。
コールバック後、通常であればすぐに通知があるはずでしたが、2週間近く何の音沙汰もありませんでした。コールバックの成功率は一般に60~80%と言われ、面接の感触も決して悪くは無かったため、この事態はショックでした。入学試験のときのように、今から別の事務所に履歴書を送ってインタビューを模索する道も無いわけではありませんでしたが、アメリカ人ではなく、ジャーナルのメンバーということ以外にさしたる特長のない私を受け入れてくれる事務所がそう簡単に見つかるとは思えませんでした。ところが半ばあきらめた頃になって、コールバックを受けた事務所から電話があり、サマーインターンのオファーをもらうことが出来ました。前半をNY、後半を東京事務所で過ごすという最高の内容で、その場で受諾しました。その後、別の事務所からも日本語の出来る弁護士を探しているというお話を頂くことができましたが、丁重にお断りしました。
周囲を見渡すと、この就職活動を通して明らかに「勝ち組」と「負け組」が分かれていました。ジャーナルのメンバーの状況は概して良く、面接を受けたほとんどの事務所から二次面接合格をもらい、どこにしようか贅沢な悩みを抱える学生も多くいました。また、ジャーナルのメンバーでなくても、生徒会の役員など課外活動に力を入れている学生や、はじめから大都市を避けて地元や田舎に絞って就職活動した学生などは、無事インターン先を見つけていたようです。一方で、留学生や1Lのときにあまり勉強をしていなかったように見られる学生の中には、インターンとしてのオファーをもらえなかったものも少なからずいました。彼らは、就職のオファーの可能性が非常に低い無償でのインターンや、弁護士事務所以外でのインターンを模索していくことになるのです。
(3) ジャーナル活動
私の所属するVanderbilt Journal of Transnational Lawは、1968年に創刊された、Vanderbiltでは二番目に歴史の古いジャーナルです。一年に5回発行され、論文の選定・編集など全ての過程は学生によって行われています。2L32名と3L30名の計62名の編集委員のうち、3Lの10名がEditor-in-Chief(編集長)を筆頭とする役員として中心的役割を果たし、残りのメンバーはヒラの編集委員として作業を手伝います。ヒラの編集委員の仕事は、もっぱらブルーブッキングという地道な作業になります。
米国の法律論文の特徴として、その引用の多さがあります。基本的ルールとして、純粋な自分の意見を述べている文章以外は、必ずその文章の間接・直接的な引用元を明記しなければいけません。学者の論文であれば、一つの論文につき少なくとも300箇所以上の引用があるのが通例です。ブルーブッキング(Bluebooking)というのは、その引用一つ一つが、形式的かつ実質的に正しいかどうかをチェックする作業のことです。引用の正しさは、当該論文の価値・説得力などを高めるだけでなく、将来の研究作業に多大な影響を及ぼすため、本文と同様に、時には本文以上に重要視されます。それだけに、ジャーナルのメンバーの大部分がこのブルーブッキングに携わっているのです。
形式的なルールは、ブルーブック(bluebook)という400ページほどの冊子に載っています。たとえば、句読点の打ち方に始まり、大文字小文字イタリックの使い分け、単語の省略方法などが詳細に定められています。特に、引用元の種類、つまり本・論文・判例などによって、引用方法が異なります。外国文献の引用方法も国別に詳細に定められており、たとえば大日本帝国憲法時代の判例の引用方法まで載っています。
The Bluebook
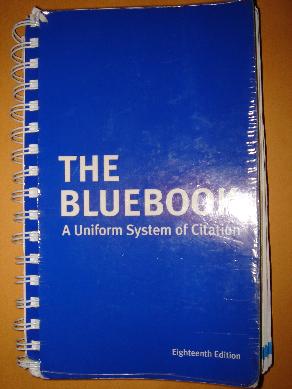
その中身
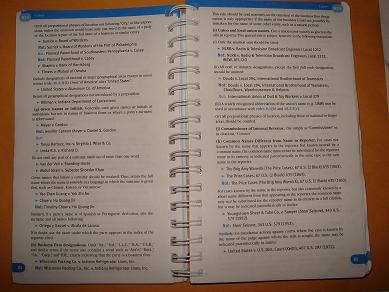
また、引用は実質的な内容も正しくなくてはなりません。たとえば、引用文献が本当に筆者の主張を裏付けているものかどうか、全て元の文献までたどって調べなければなりません。本来引用するべきところがあたかも自分の意見として述べてられていたり、空欄になっていたりする場合もあり、そのときには我々が引用として使える文献を探してこなければいけません。ですから、たった一箇所の引用であったとしても、引用元の論文100ページを全て読まなければいけない場合や、引用文献を探して図書館を数時間めぐり歩くこともあります。
一本の論文は数人の2Lに振り分けられるため、自分が担当する引用箇所数は50~100となります。通常1~2週間程度の締め切りが設けられ、授業の予習復習をこなしながらでも可能な量であるとされています。しかし実際には、たった一箇所の引用について膨大な量の論文を読んで内容を確かめなければいけなかったり、引用方法が全くブルーブックに則っておらず一からやりなおしたり、作業は遅々として進みません。私の場合、授業の予習復習や就職活動の合間だけではとても間に合わず、土日のほとんどをジャーナルに充て、さらに提出直前は徹夜作業になることがほとんどでした。秋学期中のアサインメントは5回あり、1回につき30~40時間を費やしていたと思います。私がこれほどまで真剣に取り組んだのも、このブルーブッキングが唯一ネイティブたちに勝てる分野であると知っていたからです。
最初に担当することになった論文は、ドイツ人教授の書いた「盗難絵画の国際的返却義務について」の論文でした。採用されるだけあって、論文の内容自体は非常に価値が高そう(2Lになったばかりの自分には正直なところ本当の価値はわかりません)でしたが、問題は、引用方法が全くブルーブックに則っていないことです。と申しますのも、ブルーブックはアメリカ独自のもので、アメリカのロースクールで教育を受け、かつジャーナル活動などを通して訓練をつまなければ身につくものではありません。引用の実質的正しさはともかく、形式的には正しい部分を見つけるほうが困難なほどで、私の担当部分は全て真っ赤な修正マークで埋め尽くされました。
この時期ジャーナルのメンバーに会うと、だれもがブルーブッキングに対する不平不満を口にしました。確かに時には、自分が都合の良いアシスタントとして、ただ働きをさせられているという憤りを感じることもありました。しかし、それでも私は、ジャーナルの作業を嬉々として行いました。論文のプロである教授の書いたものを、素人のしかも外国人の自分が真っ赤に修正してよいというのは、通常では考えられない特権でした。何よりも、1Lを通して味わった劣等感・疎外感を脱ぎ捨て、ジャーナルの単なる一つの歯車という存在ではあったにせよ、自分が必要とされていることがうれしかったのです。また、ジャーナルのメンバーという肩書きは、周囲の目を大きく変えました。1Lのときは私を無視したり、なんとなく冷たい態度を取ったりしていた学生もいました。しかし現金なもので、このころには、向こうから積極的に話しかけてくるようになりました。2L夏休みのインターン先が決まったことを話しても、それは決まって当然だという反応がほとんどでした。
さて、死ぬほど怖くつらかったロースクール生活も半ばを過ぎました。授業・就職活動・ジャーナルの三重苦も、運よく結果のでた今となっては、良い思い出です。この後私はさらにジャーナルにのめりこんでいくことになるのですが、それはまた次回のお話で。。。