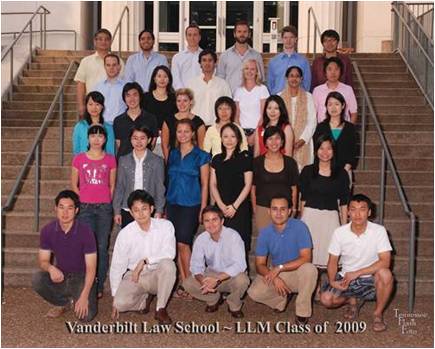J.D.攻略法その5 死ぬほど怖い1L―秋学期―希望の章 [J.D.攻略法]
前回の入学準備編からさらにご無沙汰してしまいました、J.D.卒業生のMです。5月の卒業後、NYBarの勉強・受験に集中しておりました。秋に働き始めるまで、ロースクール入学以来はじめて何の義務もない夏休みを過ごしております。さて、今回からやっと本編に入ります。死ぬほど怖い1L、死ぬほどつらい2L、そして死ぬほどだるい(私にとっては楽しかった)3Lの生活を、順を追って振り返っていきたいと思います。
(1) 概要
通常1Lの一年間は全て必修授業で、米国法の根幹となる、契約法・不法行為法・憲法・刑法・物件法・民事訴訟法などを履修します。秋学期は契約法、不法行為法、リーガルプロセス、そしてライティングの4科目15単位となっています。1Lの225人は、セクションと呼ばれる75人ずつの3つのクラスに分かれ、一年間はこのセクション単位で活動するようになります。

※リーガルライティングは、リサーチとライティングの二部構成
授業開始の前週の木・金に簡単なオリエンテーションがありました。金曜夜には、すでにメールで翌週のアサインメント(宿題)が送られてきており、週末は特に外出もせず宿題に没頭しました。しかし、要領をつかんでいないため、週末全てを使っても火曜日授業の分までは全部読みきれませんでした。
授業は原則として、悪名高き「ソクラテスメソッド」と呼ばれる教授対学生の問答方式にのっとって行われます。写真のように、クラスメイト75人の視線を浴びつつ、教授の尋問に答えるというのは、かなりの試練です。私も何度も餌食になりましたが、これはアメリカン・ローヤーになるために避けて通れない、重要な訓練のひとつとされています。ちなみに、2L・3Lになると予習をしてこない生徒も現われ、ソクラテスメソッドも幾分ゆるやかになります。

日本の法学部であれば、あまり予習は必要とされず、教授が一から全て説明するのが通常でしょう。一方、ここでは解説は一切無く、たとえばいきなり、「ミスター・ジョンソン、○○事件の事実関係を説明してください」から始まって、教授はだんだんと質問を難しくしていき、生徒が答えられなくなると別の生徒に回答を要求します。
教授は通常初回の授業時に、シーティング・チャート(座席表)に名前を書かせ、次回からもその席に座るよう指示します。教授も全ての生徒の名前は覚えられないため、シーティングチャートを使って生徒を当てるのです。私は全ての科目で最前列に座り、教授にかぶりつくようにして講義に臨みました。教授の言葉もよく聞こえ、集中力が高まりやすいからです。結構死角になって当てられにくいという隠れたメリットもあります。
(2) Contracts(契約法)
日本の民法の一部に当たり、契約重視の米国では、弁護士として避けて通れない「キモ」の科目です。担当は、O’hara(オハラ)という女性教授で、ジョージタウンロースクールを卒業し、連邦第三控訴裁判所でクラーク(裁判官助手)を勤め、シカゴ大学やジョージタウンで教えた後、2001年に当校の教授となりました。授業開始前に配られたシラバス(授業予定表)には、授業内容、スケジュール、採点方法などが5ページにわたってびっしりと詳細に書かれていました。特に、「質問方法(!)」という項目があり、「授業で分からないことがあった場合は、私のところにすぐに来てはならない。まず複数のクラスメイトに聞き、それでも分からない場合はメールで送付すること。メールによるやりとりでも解決しない場合のみ、オフィスまで訪ねてきて良い」とのこと。もっとも実際には、質問すれば優しく教えてくれる教授でした。
教授は顔写真付きのシーティングチャートを持っており、最初の一人をランダムに当て、その後はその生徒の座っている列の生徒を順番に当てました。判例の事実関係などの簡単な質問ではなく、アサインメントの内容を完全に理解してきていることを前提として、いきなり仮想問題から授業を始めるのです。授業が始まって間もない2週目、とうとう私の座る列の順番がやってきました。あたりそうな部分を予測して、かなり集中して問答を聞いていたのですが、「ではミスターM、この事件では原告の主張が一部分だけ認められていますが、それはどこですか?」と聞かれ、頭が真っ白になってしまいました。そもそもどの判例について聞かれたのかが分からず、とりあえずそれらしい判例を急いで読み返すものの、全く頭が働かず、しかたなく「分かりません」と答えました。
教授は、しょうがないなあという顔をして、私の隣のJさんを当てましたが、彼女は「すいません、いったいどの判例について答えればいいのですか?」と言います。クラス全体も、「そうだそうだ」という雰囲気になりました。つまり、教授の説明がいきなり飛んだため、クラスの大部分が理解していなかったのです。相手の質問を確認する、という基本中の基本ができなかった自分を恥ずかしく思うと同時に、ここでは発言できないものは相手にされない、と強く再認識しました。後日指名されたときには、教授の親切な誘導もあって、何とか最低限の回答は出来るようになりましたが、このクラス全員の目が集中するなかで頭が真っ白になると恐ろしい体験は今でも忘れることが出来ません。
(3) Torts(不法行為法)
日本の民法の一部で、原則として契約関係に基づかない原因により傷害や事故が発生した場合の法律関係を扱います。たとえば、幼児がいたずらでいすを引いたために転んで骨折してしまった、フットボールの試合で危険なタックルをして怪我をさせた、大量生産の薬の副作用でガンになってしまった、など多岐にわたる事例があり、裁判の多くはこの不法行為に基づいて起こされるといっても過言ではありません。
担当はHetcher(ヘッチャー)教授で、中西部の名門ウィスコンシン大学を卒業後、修士号および博士号を取得し、ロースクールは最難関のイェールを卒業、ワシントンの有名事務所アーノルド・ポーターで訴訟弁護士として働いた後、当校の教授に就任しました。ラフな格好の多い教授陣の中で、190センチの長身にジャケットとネクタイをビシッと着こなし、頭脳明晰、その立ち居振る舞いは非常にエリート然としています。実務経験に基づく具体的な解説が非常に分かやすく、たとえば医療過誤訴訟やPL(製造物責任)訴訟などは、証人の選び方が判決を左右するくらい重要であることを、実例を挙げて教えてくれます。
教授は生徒の名前を書いたカードを携帯しており、トランプのようにカードを切りながら適当に引いて当てるので、常に緊張を強いられます。ある日の主要判例は、若い女性が夜中に車で信号待ちをしていたところ、4人の男性を乗せた車に道をふさがれ、卑猥な言葉を浴びせられたり、乱暴するぞと脅されたりしたものでした。明らかにAssault(脅迫)に該当するケースです。前日に簡単な質問で当てられていたので今日はあたらないだろうと高を括っていたところ、私が男性(被告)側弁護人として当てられてしまいました。
原告側弁護人役の女生徒が大変早口なのと、自分の緊張のため、彼女が何を言っているのかよく分かりませんでしたが、とにかくこちらも何か言わなければ負けです。このときは少なくとも頭が真っ白になることは無く、ノートを読み返して何とか該当部分を探し、「被告の証言によると、彼は単に友人を面白がらせようとしただけで、脅迫の意思はありませんでした」と、苦し紛れに発言しました。すると教授が、「その通り。意思が無ければ脅迫は成立しない」と珍しく褒めてくれました。その後しどろもどろながら、教授の仲介もあって何とか生き延びることができ、授業が終わった後に、周りの学生達から「Good job! (よくやった)」と口々に言われたのが大変うれしかったのを覚えています。
私の隣には、ヴァージニア大学出身のD君が座っていました。銀縁眼鏡の、ビルゲイツのような風貌をした天才肌で、授業中もヨーグルトを食べながら、教授を感心させるような鋭い発言をしばしばします。そして、クラスメイトのほとんどが蛍光ペンを使ってテキストを塗りつぶすように読む中で、彼のテキストは真っ白なのです。それで頭に入るのかと聞いたところ、「線を引きすぎると、かえって重要な部分が見えなくなる。それに、綺麗にしておかないと、後で古本屋に売れないだろ」とのことでした。
授業中最も印象に残った判例として、パルスグラフ事件(Palsgraf v. Long Island Railroad)がありました。事件の概要は、「駅で乗客を駅員が電車に押し込んだところ、乗客の持っていた紙包みが落ちて中の花火が爆発し、数10メートル先に立っていたMs. Palsgrafの上に柱が倒れて怪我をさせた。果たして駅員はMs. Palsgrafに対して責任があるか?」というものです。この判例は歴史上最も有名な判決の一つであり、それは、Cardozo判事による判決主文(多数意見)と、Andrew判事による反対意見(判決としての効果を持たない参考意見)が、どちらも同じくらい画期的で、かつ説得力があるからです。
Cardozo判事は、1900年代前半から半ばにかけて活躍したニューヨーク州高等裁判所の裁判官(後に連邦最高裁判事)で、弱者救済のため、従来の判例を覆す独創的な判決文を多数書いたことで有名です。複雑な英語を書く法律家が多い中で、Cardozo判事の文章は簡潔明瞭で、80年以上経った今でも「Plain English(平易な英語)」の見本としてしばしば引用されます。教授の中でも評判の高い判事ですが、ある教授によれば、「彼は一生独身で、人付き合いも全くせず、法律だけに人生をささげた変人です。こんな人にまともな判決が書けるわけありません」と散々です(この辺は非常にアメリカっぽいですね)。
一方、Andrew判事の反対意見は、Plain Englishにはほど遠い長文で、何度読み返しても何を言っているのかさっぱり分からないのです。ヘッチャー教授は、ロースクールの授業にしては珍しく、一文一文を追ってまるで国語の授業のように詳細に解説してくれました。因果関係理論を川の流れを使って描写した部分は、特にお気に入りのようで、何度も「美しい」と賞賛していました。あえて簡単に解説すると、最初は透明な川の流れが、途中で茶色い泥と混ざり、さらに赤土と混ざり、結局水はにごってしまいます。これと同様に、最初は明らかだった事件の原因も、その後さまざまな事象が起こることによって、因果関係が不明確になるということなのです。
日本の判例と違って、米国の判例には決められた形式がありません。質のばらつきが激しく、意味不明のものがある一方で、この判例のように、文学作品のような高尚なものや歴史を変えるような独創的なものもあるのです。
あるクラスメイトに言わせると、教授は「Self-centered person(自己中心的人物)」とのことで、授業の本筋に関係ない質問や意見に対しては、「それは関係ない」と言って切り捨て、どんどん自分のペースで授業を進めます。一見不親切なようですが、学生、とくに1Lの質問や意見は混乱につながることが多いため、このほうがかえって分かりやすいのです。授業の後に質問に行けば、非常に丁寧に答えてくれます。ただしあまりに頭が良過ぎるためか、どこか人を小ばかにしたところがあり、生徒間の人気はそれほど高くないようです。
試験一週間前に、教授から質問をまとめてメールで送るように指示があり、私も4つほど厳選して送付しました。後日、すべての質問と回答をまとめたものがクラス全員に送られましたが、中には「漠然すぎる質問。教科書をもう一度読み直せ」などといかにも教授らしい回答がありました。私の質問には、すべてまともな回答が書いてあり、一安心でした。
(4) Legal Process(法律過程)
本校特有の科目で、契約法のように単一の法律分野を扱うのではなく、広く法哲学・法システム・法思想などを学び、法的思考力養成に資することを目的としています。担当はBrandon(ブランドン)教授で、その風貌は、めがねに髭をたたえ、常にチノパンにボタンダウンシャツという、いかにも大学教授然としています。ハロウィーン(仮装する習慣がある)の時には、そっくりの仮装をしてきた学生がいて、喝采を買っていました(写真左側が教授、右が学生)。

授業はオーソドックスなソクラテスメソッドと講義の混合形式でしたが、科目自体の抽象性もあり、非常に難しい授業でした。そんな中でも、大変印象に残った判例があったので、紹介したいと思います。「Critical Racial Theories(批判的人種論)」という法思想の分野で取り扱った「ミシガン・ロースクール事件」は、米国における人種差別という問題の深刻さを再認識させるものでした。争点は、公立大学における「Affirmative Action(積極的優先処遇)」の是非です。
Affirmative Actionとは、大学・大学院などの入学試験において伝統的に行われてきたもので、試験の点数に「ゲタ」をはかせることによって、少数民族や過去に人種差別を受けた人々を優先的に入学させるものです。この事件では、ある白人女性が、「同じ点数で合格した生徒がいる一方で、自分は白人であるため不合格となった。これは逆差別であり、法の下の平等を定めた合衆国憲法に反する」として、ロースクールを相手取って裁判を起こしたのです。事件は連邦最高裁判所まで争われ、結局9人の裁判官によって5対4という僅差で、自動的なゲタではなく、あくまで人種を一つの要素として考える場合には合憲(逆差別ではない)と判断されました。
日本ではちょっと想像できないような訴訟であったのと、証人として出廷した教授やスタッフを何人か知っていたので、大変印象に残りました。特に、私の1L時のバンダービルト・ロースクールの校長で、事件当時ミシガン・ロースクールで教えていたシブルド教授が、「Affirmative Actionの目的は、多様な人種の生徒と接することによって、人種とは関係なく多様な意見があることを知り、ステレオタイプ的な人種的偏見をなくすことである」と証言していました。この証言が判決に多大な影響を与えたことは、最高裁が判決理由で、「Affirmative Action の目的が過去の差別の社会的効果の是正のみであれば違憲だが、教育の場における多様性の実現という目的を持つならば合憲である」と述べていることからも明らかです。実際、私は入学前にシブルド教授のインタビューを読んだことがあり、当時まだ係争中だったこの事件について、教授は、「最高裁が何と言おうと、教育の場に多様性を実現するこの政策を私は支持する」と断言していました。私はそれを読んで、こういう人のもとで是非勉強したいと思ったものです。
(5)Legal Writing and Research
判例・法令・文献などの調査方法を学ぶ「リサーチ」と、文章構成・表現などの基礎に始まって、最終的には弁護士事務所のパートナー向けのメモ作成を行う「ライティング」の2部構成です。リサーチは、弁護士としての実務経験もある図書館のスタッフ、ライティングは、当校の卒業生で現在はナッシュビルで弁護士をしているローズ教授が担当です。
かつて資料の検索はすべて紙ベースで行われていましたが、現在はレクシスとウエストローという2大データベース会社が提供する電子検索が主流です。両会社は、データベースを学生に無料で提供しており、大変便利なのと、使うほどにポイントがたまって景品ももらえるため、紙ベースでの検索方法はすぐに忘れられてしまいます。オートマティック車に馴れて、マニュアル車が運転できなくなるのと同じですね。しかし、実はここに大きなからくりがあり、卒業して弁護士なってからこれらを使用すると、一分もしくは一件ごとに相当な金額が掛かってしまうのです。一度電子検索の便利さを知ってしまうと、もう紙ベースには戻れないという、ある種の中毒現象です。
リサーチ・ライティングともに、理論の講義はほとんどなく、日々少しずつ高度になっていくアサインメントをこなす形式で授業は進みました。アサインメントの提出にあたっては、11ページに渡って詳細なルールが規定してあるシラバスを参照しなくてはなりません。たとえば、提出物はすべて、「レターサイズ、片面印刷、23行、ダブルスペース(行間を2行にする)、フォントはTimes New Romanで12ポイント」で、「この意見書を書くにあたって、許可されていない一切のサポートを受けておりません」という宣誓文に署名し、提出時間を守ったことを示すスタンプを押してもらわなければなりません。契約法のシラバスでもそうでしたが、米国人、特にローヤーは、細かいルールに異常なほどにこだわります。これは、予め詳細なルールを規定することによって紛争を未然に防ぐという目的だけでなく、ルールが無いと各人の取り扱いが全くばらばらになって収集がつかなくなる、という理由もあるのです。日本のように、阿吽の呼吸・暗黙のルールといったものはまず存在しません。
自分にとっては大変実践的で面白く、最も力を入れた科目でもありました。アサインメントの提出前にはほぼ徹夜になることもしばしばでした。Citation(判例や文献の引用)に関しては、詳細な統一ルールがあり、そのルールだけでブルーブックという一冊の本が発行されているほどです。ルールは複雑ですが、たとえば判例であれば一目で「いつ・どこの裁判所で・誰が誰を訴え・どこを調べれば判例が見つかるか」が分かるという、非常に効率的なものです。一文ごとにルールを調べるという地道な作業が要求されるため、適当に終わらせてしまっているクラスメイトもいましたが、私はとにかく時間を掛けて作業しました。提出後に教授から、あなたのCitationは一番正確だったと褒められました。実はこの時期、様々な劣等感と疎外感に打ちひしがれていた自分にとって、この一言は神の声に等しく嬉しかったのです。語学力ではネイティブには一生勝てないが、ノンネイティブの自分にも勝てる分野があるということがわかり、また、このことがその後のジャーナルへの挑戦と繋がっていくのでした。
(6)勉強方法

アメリカ人はどこでも勉強します。地べたや階段に座って教科書を読んでいるものもいますし、私も、暖かい9月10月には、芝生の上で勉強したこともあります。日本の法学部の場合、ごく一般的な勉強方法は、ろくに予習もせず(まじめな学生は)授業に出て、教授の説明をノートに取り、試験直前にノートや教科書を読み返すといったところでしょう。しかしここ米国のロースクールでは、授業は予習を前提としたソクラテスメソッドで進められ、一学期で1,000ページにも及ぶ教科書を消化します。よって、日々の予習・復習の積み重ねが必須で、具体的には、「アサインメント」を読み→重要判例につき「ブリーフ」を作成し→授業に出てノートを取り→ブリーフとノートをあわせて「アウトライン」を作成し→試験前にアウトラインを凝縮した「チェックリスト」を作成することになります。
毎回授業前には、教科書の20ページ程度をアサインメント(宿題)として読んでくるよう指示が出ます。20ページ程度といっても、教科書は細かい字でびっしりと、専門用語で埋め尽くされているため、最初のうち1時間に読めるのはせいぜい5ページ程度です。教科書は、いわゆる概説書・基本書といった理論を解説したものではなく、判例のダイジェストを集めた「ケースブック(判例集)」と呼んだほうが正確でしょう。判例を読む際には、ピンク・緑・オレンジ・青・黄色の5色の蛍光ペンを使用するのが一般的です。たとえば、過去の裁判記録および結論をピンク、事実関係を緑、争点および反対意見をオレンジ、ルールを青、判決理由を黄色というように塗ります。意味不明の判例を、少しでも読みやすくしようという工夫なのです。
また、ただ判例を読んだだけでは、授業での教授の尋問に耐えることは困難なため、重要判例について、要点(事実関係・論点・判決・判決理由など)を1枚にまとめた「ブリーフ(要約書)」を作成します。そして授業にはブリーフを持って望み、教授や生徒のコメントを補足する形でノートを取っていくのです。期末試験は、前述のように教科書1,000ページのほとんどが範囲となるので、試験前に教科書やノートを読み返す時間はありません。よって、日ごろから、ブリーフおよびノートの重要点を編集し、アウトラインと呼ばれるまとめノートを作ることが重要です。アウトラインは通常50~100ページほどの長さになるため、試験直前には、アウトラインをさらに凝縮・編集し、5~10ページほどのチェックリストにします。なお、法律関係の出版社も、各科目の要点をまとめたアウトラインを市販しています(「エマニュエル」など)が、実際の授業とは必ずしも一致せず、自分でアウトラインを作ったほうが頭に入りやすいため、参考程度にとどめておいたほうが良いと思います。
学生の中には、スタディーグループを作って集団で勉強をするものもいます。ただ、集団によって効率を上げるというよりは、孤独を紛らわせるための仲良しグループといった意味合いのほうが強いように思えました。私の場合、日々のアサインメントの消化で手一杯でした。また、外人で、クラスでの受け答えもしどろもどろな私を受け入れてくれる(少なくとも優秀な)スタディーグループも無かったというのが正直なところです。ただ、試験直前には、契約法と不法行為法の過去問題につき、中国出身のJ.D.のS君とそれぞれ一日ずつディスカッションを行い、疑問点を解消し合いました。彼はノースウェスタン大学で社会学修士号を取得しており英語はしっかりしているのですが、私のほうが少し先に勉強を進めていたため、勉強のパートナーとしてはお互いにちょうど良かったのです。
(7)日常生活
典型的な平日のスケジュール

典型的な休日のスケジュール

毎日の予習(宿題)・復習量が膨大であるため、基本的に勉強中心の生活でした。むしろ、人間として最低限の生活をしている時間(睡眠・食事・トイレなど)を除けば、土日も含め全て勉強していると言っても過言ではありません。具体的には、秋学期中は、散髪0回、外食(除くファーストフード系)1回、レジャー・旅行0回、でした。私は語学のハンディがあるため、やや極端な部分もありますが、大部分の1Lは、ほぼ同じような生活をしていました。ずっと髪を伸ばしっぱなしにしていたら、学生食堂のおばちゃんに、ナイスな髪型ね、と褒められました。
周囲のクラスメイトに聞いても、大抵1科目につき、2~3時間は予習にかかっているといいます。平均で一日3科目ですから、単純計算でも、授業で3時間、予習で6~9時間必要になります。私は当然彼らより読み書きのスピードが遅いので、彼らの1.5~2倍の時間は必要です。予習だけで一日は終わってしまい、加えて復習やライティングの提出物もあります。平日の睡眠不足とストレス解消のため、土日の朝は多少ゆっくりと寝るものの、やはりほとんどの時間は勉強せざるを得ません。
10月の半ばに、金・月と週末を合わせ、1Lのみ対象の4日間のミニブレイクがありました。学校が始まって2ヶ月弱、相当ストレスや疲れが溜まっていたため、ゆっくりと寝られるのは非常にうれしかったのを覚えています。もっとも、4日間すべて休むものは周囲にもほとんどおらず、私も、溜まっていた各科目の復習と、ライティングの提出物(法律意見書作成)に4日間を費やしました。また、11月の第4週、サンクスギビング(感謝祭)の前後には、秋季休暇として全校が9日間休みになりました。LLMの友人の中には、ニューヨークやフロリダに旅行する者もいましたが、私は全く旅行などする気も起こらず、9日間すべて(睡眠をしっかりとりつつ)勉強しました。このころになると、勉強する日常があまりに当たり前になっており、勉強しないとかえって不安やストレスを感じるようになっていました。客観的にはかなりの変人でないと、J.D.は生き残れないのかもしれません。
(8)期末試験
秋季休暇終了後、一週間だけ授業があり、期末試験期間に突入しました。ロースクールの成績は、提出物の多いライティングなどの科目を除き、ほぼ100%期末試験のみで決まります。教授によっては、クラス参加・発言につきプラスの評価を加えることがありますが、少なくとも1Lについては、授業を休む者はいませんし、教授が学生をほぼ均等に当てるので、ほとんど差はつきません。
契約法・不法行為法・リーガルプロセスとも、(量が膨大なことを除いては)オーソドックスな事例問題でした。たとえば、不法行為法では、一時間相当の設問が、問題文だけで4ページあり、時間との戦いでした。要約すると、「飛行機の操縦士と副操縦士がサボってコクピットから出ていたところ、誤ってドアをロックしてしまった。そのまま進むとホワイトハウスに突入してしまうとの知らせを受けた共和党出身大統領は、ミサイルで飛行機を打ち落とした。訴訟の可能性と予想される結果について述べよ」となり、一見簡単な事例のようですが、操縦士が客室常務員に感染症をうつしていたり、客室乗務員が乗客にコーヒーをこぼしてやけどさせたり、飛行機の落ちた地域が民主党支持者の多いところであったり、とても時間内にカバーしきれないような細かい争点が多く含まれていました。
試験はどれも難しく、時間(と語学力)が足りなかったため、量をかくことはあきらめ、とにかく答案構成と時間配分を重視し、重要論点らしきものを押さえることを心がけました。試験終了直後は呆然としていたものの、しばらくして考え直してみると結構書けていた気がして、もしかしたら最初の学期からオールAを取ってしまうのではないか、などと期待しました。その期待はもろくも打ち砕かれ、暗黒の時代がスタートすることになるのですが、それはまた次回のお話で。。。